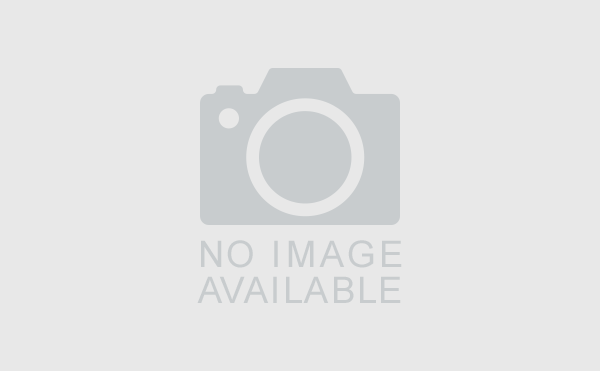葬式、相続
前回の続き、
これからの書くことのほとんどは、専門家に任せてもなんら問題ないことですが、『全て自分でやる』をコンセプトにしました。
まず、7日以内にやること、実際の動き。父は隔離されていたため、約一ヶ月近く会いに行けませんでした。遺体は見ることができず、ほとんどの手続きは、業者が行いました。火葬も業者が行い、遺骨が、戻ってくるのに、3日かかりました。死亡診断書、火葬埋葬許可書もその時返してもらいました。
普通に人を集めて、葬儀をできる状況でないため、子と母だけで、近所の寺で、初七日法要をしてもらい戒名をつけてもらいました。葬儀は、この後も、社会情勢のため、密葬とし、いずれお別れ会(この時点では、一周忌に)を予定する気でいました。納骨は、早いうちと、戒名をもらったりして、3週間以内に行いました。孫と子でできるだけやれる事をしようとなり、49日には、孫と子と母で、食事会をしました。次は、新盆で集まりました。お墓に行って、念仏をあげてもらいました。
遺骨が戻ってから翌週に、市役所に行って、後期高齢者保険・介護保険の資格喪失届、葬祭費の請求(後期高齢者健康保険から出るもの)、住民票の抹消届、世帯主の変更届をしました。この時、本籍地であれば、戸籍謄本をもらっておく様にしてください。後に死亡した事実の入った戸籍謄本が必要になります。詳しくはここ。
年金についても、役所に相談しましたが、年金事務所に行くように、言われ、(遺族年金に変更のため)年金事務所に電話連絡したところ、予約が必要と言われたので、予約を取りました。(一ヶ月先になりました。)
以上の内容は、14日以内のものも入っています。遺族年金の手続きは、5年以内と書いてありますが、年金の停止等で、連絡をしなければ、ならないので、予約を取った日に、同時に済ませました。
自宅から電話で、水道、電気、ガス、電話等の引き落とし名義変更をしました。
電話番号は、それぞれ、引き落とし通知書とか、年金の通知書で、調べてみました。市役所に行った時、公的なものは、一覧表をもらいました。
この時点で、銀行口座、証券会社には、まだ、連絡しませんでした。死亡した事実が知れると、相続協議が終わるまで、口座は凍結されるそうです。どの口座に、どれだけ財産が残っているか。通帳はあるか、ネットで検索して、連絡先電話番号、銀行の相続手続きが、どの様に進むかを、把握しておきましょう。
相続税を払う必要がある場合は、10ヶ月以内に終わらせなければいけません。私の場合は、相続税の基礎控除額以下だったので、余裕があると思っていました。10ヶ月経つと、税務署から、概算を知らせる要にと書類が送られてきます。これは送り返さないと、調査が入る可能性があると思うので、概算を書いて、返送しました。地価の見積もりが、よくわかりませんでしたが、固定資産税の通知書に書いてあるものに所有割合を、掛けて、算出しました。
この辺の事は、相続として、のちにまとめます。
相続でする事、
一連の葬儀式、
- 葬式、通夜、告別式(私は、密葬でしましたので、詳しくは自分でお調べください。)
- 初七日、49日、納骨、香典返し、新盆、一周忌、年賀の欠礼葉書